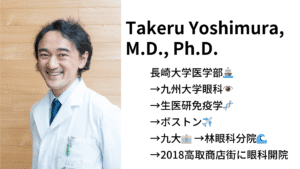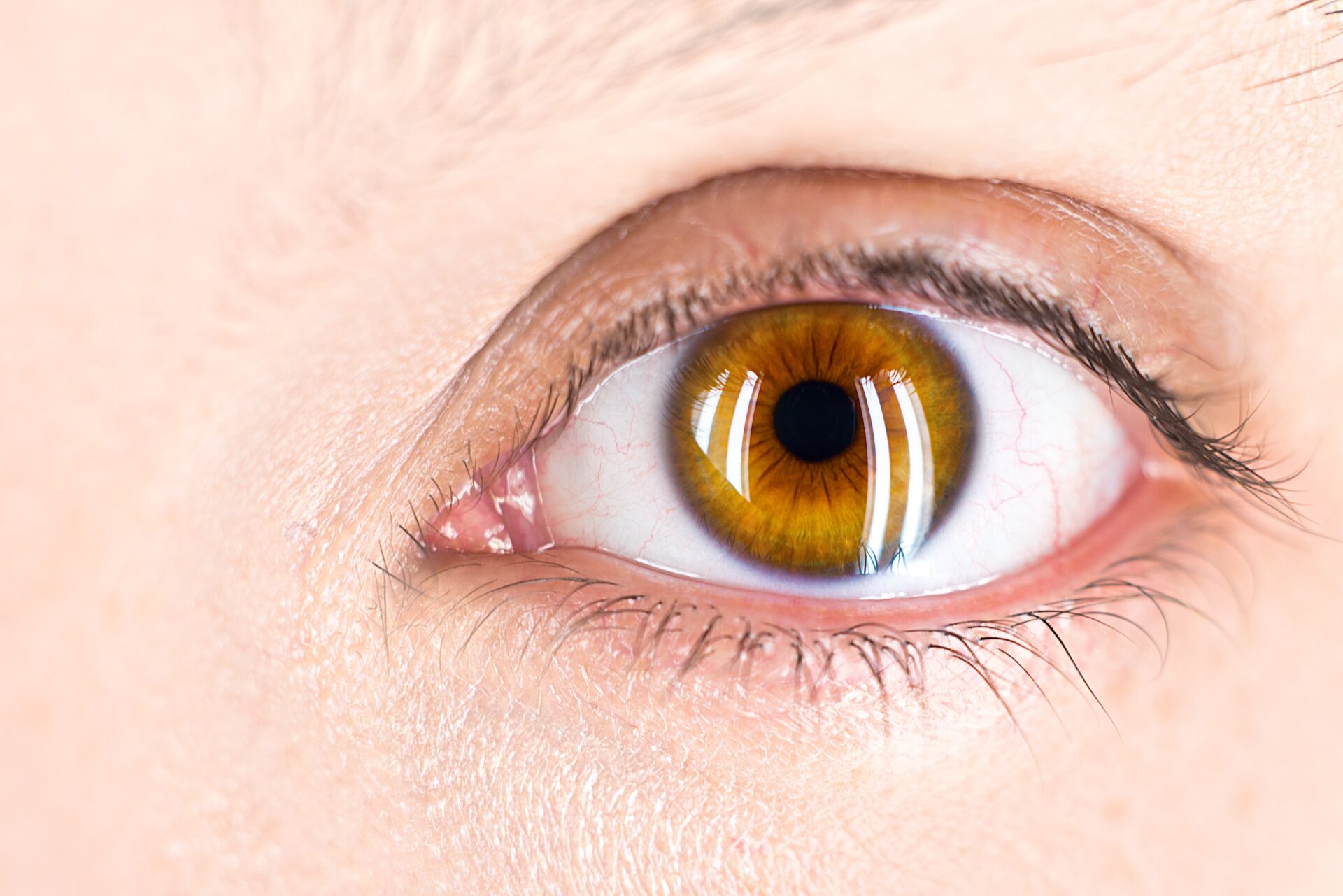「脳卒中になってから、なぜか物にぶつかりやすくなった」
「本を読んでいても、どこを読んでいるのか分からなくなる」
「ものが二重に見えて、どうにも気持ちが悪い」
この記事では、脳卒中後に生じる視覚の問題について、その原因、ご自身の状態を把握するための検査、今後の見通し、さらに生活の質を改善するためのリハビリテーションまで、順を追って解説します。
本文で用いる「脳卒中」という言葉は、脳の血管が詰まるタイプ(脳梗塞)と、脳の血管が破れるタイプ(脳出血、くも膜下出血)を合わせた呼び名です。原因に関わらず、脳が損傷を受けることで同様の視覚症状が起こりうるため、この記事では「脳卒中」という言葉で統一してご説明します。
見え方の変化の原因は「脳」
見え方の変化は「脳」に原因があります。適切な対処を行うことで、生活の質を改善することができます。
脳卒中後の見え方の変化は、多くの場合、目そのものの病気ではありません。
目から入ってきた情報を処理する「脳」の一部が損傷を受けたために起こる症状です。
症状には、視野が半分欠けてしまうものや、物が二重に見えるもの、さらには片側の空間を認識しにくくなるものなど、さまざまなタイプがあります。
しかし、適切な検査でご自身の状態を正確に把握し、症状に合わせたリハビリテーションや工夫を行うことで、残された視機能を最大限に活用し、安全で快適な生活を送ることが十分に可能です。
なぜ、脳卒中の後に「見えにくさ」が起きるのか
私たちの「見る」という行為は、眼球と脳の連携プレーで成り立っています。
眼球がカメラのレンズだとすれば、脳は撮影した画像を処理して意味を理解するコンピューターです。脳卒中は、このコンピューターの一部を損傷させるため、カメラ(眼球)が正常であっても「正しく見えない」状態が生じます。
脳卒中後に起こる視覚の問題は、大きく3つのタイプに分けられます。
1. 視野が欠ける(同名半盲)
視野(しや)とは、一点を見つめている時に見える範囲のことです。
同名半盲(どうめいはんもう)は、両目の視野の同じ側(右半分、あるいは左半分)が見えなくなる状態を指します。脳卒中後に起こる視野障害で最も多いものです[5]。
例えば、右同名半盲の方の場合、視界の右半分にある人や物に気づきにくくなります。
そのため、右側にある障害物にぶつかってしまったり、食事の際に右側のお皿に気づかなかったりすることがあります。
読書の際には特に困難を感じることがあります。
右同名半盲の場合、次に来る単語が見えないため、文章を追うのが難しくなります。
一方、左同名半盲の場合は、次の文の始まりを見つけるのが難しくなります[8]。
この症状は、脳の後方に位置する視覚情報を処理する中枢(後頭葉)への血流が途絶えることで生じます。
2. 物が二重に見える(複視)
物が二重に見える症状を複視(ふくし)と呼びます。
これは、左右の目の視線が、見たい対象に対して正確に合わなくなるために起こります。
脳卒中によって、眼球を動かす筋肉をコントロールする神経が麻痺することが主な原因です。片方の目が正常に動かなくなると、左右の目に映る映像にズレが生じ、脳がそれを一つの像としてまとめられなくなるのです[4]。
複視があると、階段の上り下りや物との距離感がつかみにくくなり、転倒のリスクが高まるなど、日常生活に大きな支障をきたします。
3. 見えているはずなのに、認識しづらい(半側空間無視・視覚失認)
これは少し複雑な症状です。
視野の欠損や目の動きの異常がないにもかかわらず、片側の空間にあるものに注意が向きにくくなる状態を半側空間無視(はんそくくうかんむし)と呼びます。
特に右側の脳に損傷を受けた場合に、左側の空間への注意が障害されることが多く報告されています。
食事の際に左半分だけ食べ残してしまったり、左側から話しかけても気づかない場合があるのは、この症状が原因かもしれません[2]。
ご本人に自覚がないことも多く、周囲のご家族が先に気づく場合も少なくありません。
今後どのように変化するのか? 回復の見通しについて
脳卒中後の視覚症状が、今後どのように変化していくのかは、誰もが最も気になることでしょうか。
症状のタイプによって、回復の見通しは大きく異なります。
視野の欠損(同名半盲)の見通し
残念ながら、一度失われた視野が自然に回復することはまれです[7]。
特に、脳卒中の発症から3〜6ヶ月を過ぎても残っている視野の欠損は、永久的なものとなる可能性が高いとされています。
そのため、「視野を元に戻す」ことよりも、「残された視野を最大限に活用する方法を学ぶ」ことが、リハビリテーションの主な目標となります。
複視(物が二重に見える)の見通し
眼球を動かす神経の麻痺による複視は、比較的良好な回復が見込めます。
多くの場合、発症から数ヶ月で症状が大きく改善し、完全に元に戻ることもあります[4]。
回復するまでの期間、症状を和らげるための対症療法が中心となります。
半側空間無視の見通し
半側空間無視は、同名半盲に比べて自然回復の可能性が高いとされています。
ある研究のまとめでは、発症後6ヶ月後には約半数の患者さんで回復が見られたと報告されています[2]。
初期の症状が重度であるほど、後遺症として残りやすい傾向はありますが、適切なリハビリテーションによって改善が期待できる症状といえます。
眼科で行う検査と、それによって分かること
脳卒中後の見えにくさで眼科を受診した場合には、いくつかの専門的な検査を行い、症状の原因を正確に評価します。
- 視野検査
ハンフリー視野計などの機器を使い、どの範囲が見えていて、どの範囲が見えていないのかを精密な地図のように描き出します。これにより、同名半盲の有無や程度を客観的に評価できます。 - 眼球運動検査
視能訓練士が、眼球の動きをあらゆる方向から詳細に確認します。どの筋肉がどの程度麻痺しているのかを調べることで、複視の根本原因を特定します。 - 光干渉断層計(Optical Coherence Tomography, OCT)検査
「光干渉断層計(OCT)」は、網膜の状態を詳細に調べるための医療機器です。網膜の神経線維の厚みを測定するこの検査では、脳の損傷が長期間にわたると、その影響が網膜にまで及び、神経が薄くなる現象(逆行性変性)が起こることが分かります。この変化を捉えることで、視覚障害がいつ頃から起きているのか(陳旧性か、新しいものか)を客観的に判断する手がかりになります[1]。
これらの検査結果は、今後のリハビリテーションの方針を決める上で非常に重要な情報となります。
生活の質を改善するためのリハビリテーションと対処法
脳卒中後の視覚障害に対するアプローチは、失われた機能を取り戻す「回復」よりも、残された機能を活かして生活する「代償」や「適応」が中心となります。
視野の欠損(同名半盲)に対して
- 探索訓練(サッカード訓練)
見えない側に意識的に、素早く視線を動かすトレーニングです。視能訓練士の指導のもと、より効率的に周囲の情報を集める目の動かし方を学びます。これにより、物にぶつかるリスクを減らしたり、読書速度を向上させたりすることが期待できます[5]。 - プリズム眼鏡
眼鏡に特殊なプリズムレンズを装着する方法です。これは視野を広げるものではありませんが、見えない側にある物体の像を、見えている視野の端へ移すことで、「何かがそこにある」と気づくきっかけになります。特に歩行中の安全性を高める効果が報告されています[3]。
複視に対して
- フレネル膜プリズム
眼鏡に貼り付けるシール状のプリズムです。光の進む方向を曲げることで、左右の目の映像のズレを補正し、物が一つに見えるように調整します。神経麻痺の回復過程で度数が変化しても、簡単に貼り替えることができるという利点があります。 - 遮閉
プリズムでも複視が解消されない場合は、片方の目を眼帯や半透明のテープで覆い、片目で物を見る方法がとられます。これにより、不快な二重に見える感覚をなくすことができます。
半側空間無視に対して
- プリズム順応療法
視野を意図的にずらす特殊なプリズム眼鏡をかけて、腕を伸ばして目標物を指差すといった課題を繰り返し行います。これにより、脳の空間認識を再調整し、無視している空間への注意を促す効果が期待できます[6]。
社会生活における注意点:自動車の運転について
脳卒中後に視覚障害が残った場合、自動車の運転には特に注意が必要です。
日本の道路交通法では、普通免許を更新・取得するために必要な視力と視野の基準が厳密に定められています[9]。
- 両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること。
- 一眼の視力が0.3に満たない者、若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。
完全な同名半盲がある場合、視野が150度という基準を満たせないため、法律上は運転できません。これは、ご自身だけでなく他の人の安全を守るためにも非常に重要です。
視野障害の程度によっては基準を満たす可能性もありますが、自己判断は非常に危険です。必ず視野検査を受け、ご自身の状態が運転の基準を満たしているかどうか、専門家による評価を受けてください。
まとめ
脳卒中後に生じる「見えにくさ」は、日常生活のさまざまな場面に影響し、ご本人やご家族にとって大きな不安の種となります。
しかし、その原因は目そのものではなく脳にあり、症状の種類によって回復の見通しや対処法が異なります。
まず、ご自身の見え方がどのような状態なのかを専門的な検査で正確に把握することが重要です。
その上で、ご自身の症状に合ったリハビリテーションや、日常生活での工夫を粘り強く続けることで、再び安全で豊かな生活を取り戻すための一歩を踏み出せます。
見え方についてお困りのことがあれば、まずは専門家に相談し、適切な評価を受けることが大切です。
参考文献
- Jindahra, P., Petrie, A. and Plant, G.T. (2012) ‘The time course of retrograde trans-synaptic degeneration following occipital lobe damage in humans’, Brain, 135(5), pp. 1613-1620.
- Kam, J.H., Secgin, H., Tang, Y.H., Cheng, C.P., Singh, A.K., Demetres, M.R., Chen, C., Corbetta, M. and Chee, M.W.L. (2024) ‘Recovery of Visuospatial Neglect With Standard Treatment: A Systematic Review and Meta-Analysis’, Stroke, 55(6), pp. 1475-1484.
- Peli, E. (2000) ‘Field expansion for homonymous hemianopia by optically induced peripheral exotropia’, Optometry and Vision Science, 77(9), pp. 453-464.
- Pollock, A., Hazelton, C., Henderson, C.A., Ang-Lee, K., Dhillon, B., Langhorne, P. and Brady, M.C. (2022) ‘Interventions for disorders of eye movement in people with stroke’, Cochrane Database of Systematic Reviews, (9), CD008389.
- Pollock, A., Hazelton, C., Rowe, F.J., Saily, A., Little, L., Langhorne, P. and Brady, M.C. (2019) ‘Interventions for visual field defects in people with stroke’, Cochrane Database of Systematic Reviews, (5), CD008388.
- Yang, Y., Li, S., Zhang, Y., Dong, Q. and Wang, Y. (2023) ‘Short-term effect of prism adaptation treatment on the severity of unilateral spatial neglect following right hemispheric stroke: A systematic review and meta-analysis’, Journal of Rehabilitation Medicine, 55, jrm4254.
- Zhang, X., Kedar, S., Lynn, M.J., Newman, N.J. and Biousse, V. (2006) ‘Homonymous hemianopias: clinical-anatomic correlations in 904 cases’, Neurology, 66(6), pp. 906-910.
- Zihl, J. (2005) ‘The rehabilitation of hemianopic dyslexia’, Neuropsychological Rehabilitation, 15(3-4), pp. 463-477.
- 警視庁. 適性試験の合格基準. https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/annai/other/tekisei03.html
![たける眼科 | 福岡市早良区 高取商店街[西新駅/藤崎駅]](https://takeru-eye.com/wp-content/uploads/2022/10/takeru_logo_for-WP-header.png)