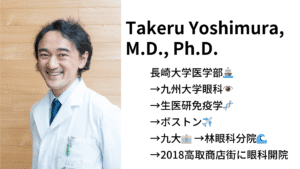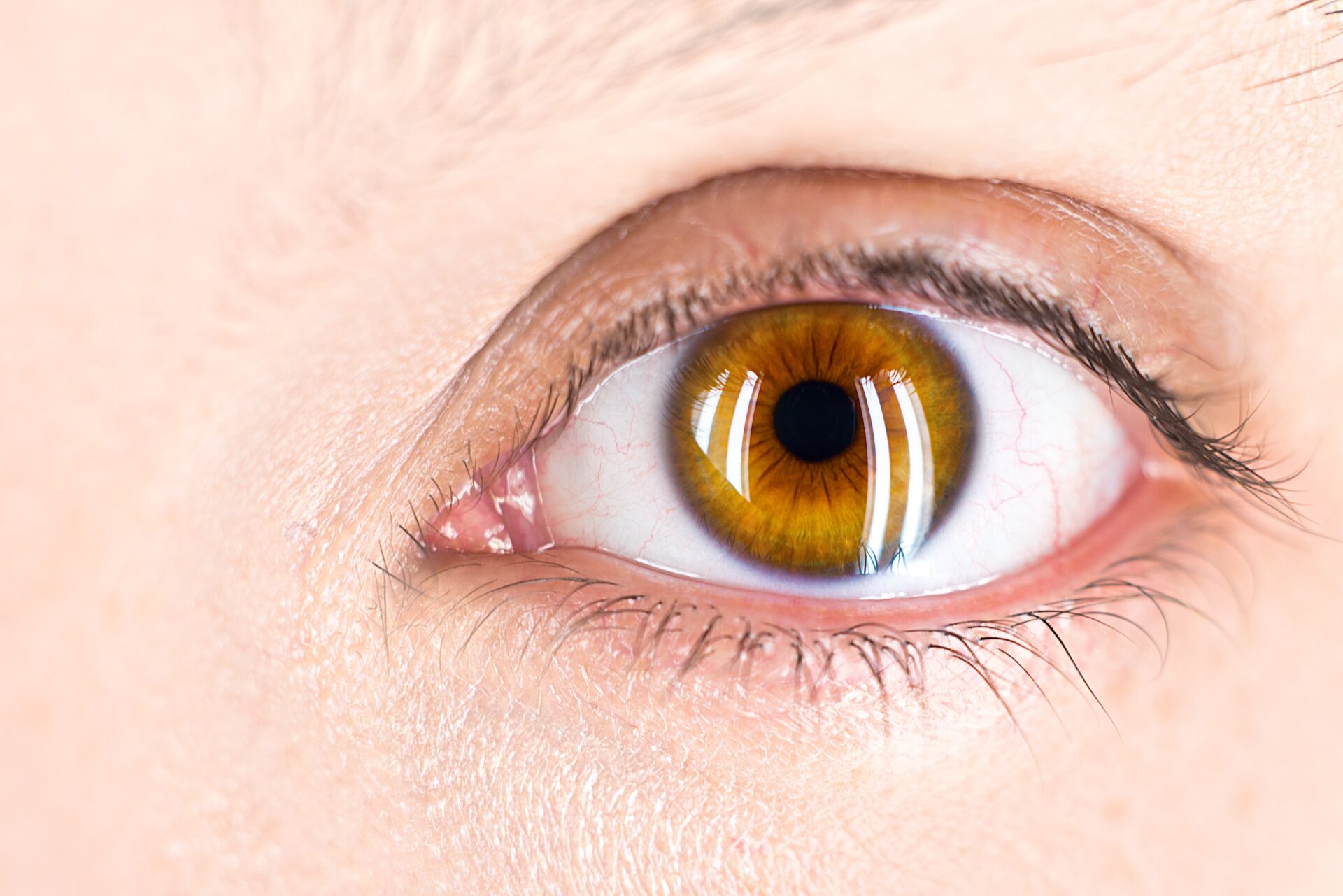夜寝ている間に特殊なコンタクトレンズを装用し、日中の視力を回復させるオルソケラトロジー。眼鏡やコンタクトレンズなしで過ごせる解放感から、特にこどもの近視進行抑制治療として、多くの方がこの治療を選択されています。
便利さの一方で、「レンズを夜つけたまま寝て、目に問題は起きないのだろうか」という不安を感じる患者さんや、そのご家族も少なくありません。
オルソケラトロジーは、定められたレンズケアを確実に行うことで、安全性が確保される治療法です。 角膜感染症という重篤な合併症のリスクはゼロではありませんが、そのリスクは一般的なコンタクトレンズと同程度であり、正しい知識と実践によって、そのリスクを管理することができます。
この記事では、オルソケラトロジーに伴う角膜感染症の「実際の発生頻度」「原因」「予防法」について、科学的な根拠を基に詳しく解説していきます。
角膜感染症は、どのくらいの頻度で起こるのか?
角膜感染症は、オルソケラトロジーに限らず、すべてのコンタクトレンズで起こりうる合併症です。その発生頻度を正しく理解することは、安全性を考える上で非常に重要になります。
近年の信頼できる研究報告によると、オルソケラトロジーによる角膜感染症の発生頻度は、患者さん1万人あたり年間で5.4人から7.7人程度とされています¹˒²。
この数字だけを見ても、多いのか少ないのか分かりにくいかもしれません。
身近な例として、日中に使用する2週間交換などのソフトコンタクトレンズ(SCL)の角膜感染症リスクとほぼ同等であることがわかっています¹。一方で、レンズをつけたまま眠ることが推奨されていないソフトコンタクトレンズを装用したまま眠るケース(Extended Wear)と比較すると、オルソケラトロジーのリスクは大幅に低いことも示されています⁶。
こどものリスクが大人より高い理由
ここで、非常に重要なデータがあります。
ある大規模な調査では、角膜感染症の発生率を年齢で分けると、こども(18歳未満)で1万人あたり年間13.9人であったのに対し、大人(18歳以上)では0人であったと報告されています²。
この差は、こどもの角膜が大人より弱いから、というわけではありません。
原因は、レンズの取り扱いにおける「衛生管理の実行度」にあると考えられます。レンズケアの各ステップを毎日欠かさず、注意深く行うことは、こどもにとっては難しい場合があるでしょう。
つまり、こどものオルソケラトロジー治療を安全に進めるためには、保護者の方による毎日の仕上げチェックや、時には管理そのものを行うといった、ご家族の積極的な関与が不可欠なのです。オルソケラトロジーの安全性は、レンズそのものの性能だけでなく、使用者とそのご家族の衛生管理への意識に大きく左右されます。
なぜ、角膜感染症が起きてしまうのか
では、どのような時に角膜感染症は発生するのでしょうか。
原因となる微生物の多くは、実は私たちの身の回りに常に存在しています。
感染症の主な原因菌
オルソケラトロジーによる角膜感染症の原因として、特に多く報告されているのが緑膿菌(Pseudomonas aeruginosa)とアカントアメーバ(Acanthamoeba)です³。
緑膿菌は、湿った環境を好む細菌です。適切に洗浄・乾燥されていないレンズケースの中などで繁殖することがあります。
アカントアメーバは、水道水や土の中など、自然環境に広く存在する微生物です。健康な目であれば、角膜のバリア機能によって侵入を防ぐことができます。しかし、レンズ装用によって角膜に微細な傷がついた状態の時に、アカントアメーバが付着したレンズが角膜に接触すると、感染を引き起こすことがあります⁴。アカントアメーバ角膜炎は治療が非常に難しく、重篤な視力障害を残す可能性がある、特に注意すべき感染症です。
リスクを高める具体的な行動
角膜感染症は、ある日突然起こるわけではありません。多くの場合、日々のレンズケアにおける、ささいな油断の積み重ねが引き金となります。
- 水道水の使用
これは、アカントアメーバ角膜炎の最大の原因であり、絶対に避けなければならない行為です。レンズをすすぐ、ケースを洗う、指が濡れたままレンズに触れるなど、いかなる形であれ、レンズや付属品が水道水に触れることは極めて危険です⁵。ボトル入りの水や蒸留水も安全ではありません。 - 不適切な手指の洗浄
レンズに触れる前に、石鹸で手指を十分に洗わないと、手に付着した細菌がレンズを介して目に入ってしまいます。 - レンズケースの汚染
レンズケースは、単なる入れ物ではありません。洗浄を怠ったケースは、細菌が繁殖するための温床、いわば「細菌の培養器」になってしまいます。古いケア用品を継ぎ足して使う、ケースを毎日洗浄・乾燥させない、長期間交換しない、といった行為は、レンズを細菌で汚染させる原因となります。
これらのリスクは、すべて「予防可能」なものです。次のセクションで、具体的な予防法を解説します。
角膜感染症を防ぐための「3つの鉄則」
オルソケラトロジーを安全に続ける秘訣は、特別なことではありません。日々の基本的なレンズケアを、手を抜かずに毎日続けることです。
鉄則1:レンズに触れる前には、必ず丁寧な手洗い
レンズのつけ外しの前には、必ず石鹸と流水で指の腹や爪の間まで丁寧に洗い、清潔なタオルで完全に乾かしてください。濡れた手でレンズを扱うと、水道水に含まれるアカントアメーバが付着するリスクがあります。
鉄則2:「水道水厳禁」を徹底する
レンズとレンズケースには、絶対に水道水を使用しないでください。これはアカントアメーバ角膜炎を防ぐ上で最も重要なルールです⁸。「少しだけなら」という油断が、深刻な事態を招く可能性があります。レンズやケースのすすぎには、必ず専用の保存液や、指示されたケア用品を使いましょう。
鉄則3:レンズとケースを正しく洗浄・管理する
- レンズの洗浄
レンズを外したら、毎日必ず洗浄が必要です。洗浄・保存液を数滴レンズに落とし、指の腹でレンズの両面を丁寧にこすり洗いします(Rub & Rinse法)。 目に見えないタンパク質や脂質の汚れがレンズに残っていると、それを「エサ」にして細菌が繁殖しやすくなります。汚れは、いわば細菌が住み着くための「すみか」を提供してしまうのです⁹。こすり洗いをすることで、この「すみか」ごと物理的に剥がし落とすことができます。 当院では、定期検査の際に患者さんのレンズを顕微鏡で拡大して観察し、こうした微細な汚れが残っていないかを厳しくチェックしています。これにより、日々のレンズケアが正しく行えているかを確認し、より安全に治療を続けていただけるようサポートしています。 - レンズケースのケア
レンズケースも、レンズと同様に毎日ケアが必要です。中の古い液を完全に捨て、新しい保存液ですすいだ後、清潔なティッシュで水気を拭き取り、キャップを開けたまま自然乾燥させます。そして、レンズケースは1ヶ月から3ヶ月ごとに必ず新しいものに交換してください。
眼科での定期検査が、目の安全を守ります
オルソケラトロジーは、ただレンズを処方して終わり、という治療ではありません。安全を確保するためには、眼科医による定期的な診察が不可欠です。
定期検査は、視力がきちんと出ているかを確認するだけが目的ではありません。レンズによって角膜の形状が適切に変化しているか、角膜に傷や酸素不足などの負担がかかっていないか、アレルギー反応は起きていないかなど、専門的な視点で目の健康状態を隅々までチェックします。
また、患者さんが毎日使用しているレンズそのものの状態(傷、汚れ、変形の有無)も確認します。レンズの状態は、目の安全に直結するためです。
定められたスケジュール(例:翌日、1週間後、1ヶ月後、3ヶ月後、以降3ヶ月ごとなど)での受診は、治療を安全に継続するための重要な約束事です。目に痛み、充血、かすみ、めやに、光がまぶしいといった異常を感じた場合は、次の受診日を待たず、直ちにレンズの装用を中止し、速やかに眼科を受診してください。
まとめ
オルソケラトロジーは、日中の快適な裸眼生活をもたらし、こどもの近視進行を抑制する有効な選択肢の一つです。
その安全性は、「使用者の適切なレンズケアの実践」という土台の上に成り立っています。角膜感染症のリスクは確かに存在しますが、その発生頻度は低く、リスクを高める原因のほとんどは、不適切なレンズケアに起因します。
「水道水は絶対に使わない」「レンズとケースは毎日正しく洗浄する」「定期検査を欠かさない」。
これらの基本的なルールを日々守ることが、ご自身の、そしてこどもの大切な瞳を未来にわたって守ることにつながります。
参考文献
- Hiraoka, T., Matsumura, S., Hori, Y., Kamiya, K., Miyata, K. and Oshika, T. (2025) ‘Incidence of microbial keratitis associated with overnight orthokeratology: a multicenter collaborative study’, Japanese Journal of Ophthalmology, 69(1), pp. 139-143.
- Bullimore, M.A., Sinnott, L.T. and Jones-Jordan, L.A. (2013) ‘The risk of microbial keratitis with overnight corneal reshaping lenses’, Optometry and Vision Science, 90(9), pp. 937-944.
- Kam, K.W., Yung, W., Li, G.K.H., Chen, L.J. and Young, A.L. (2017) ‘Infectious keratitis and orthokeratology lens use: a systematic review’, Infection, 45(6), pp. 727-735.
- Scanzera, A.C., Tu, E.Y. and Joslin, C.E. (2021) ‘Acanthamoeba Keratitis in Minors With Orthokeratology (OK) Lens Use: A Case Series’, Eye & Contact Lens, 47(2), pp. 71-73.
- Watt, K. and Swarbrick, H.A. (2005) ‘Microbial keratitis in overnight orthokeratology: review of the first 50 cases’, Eye & Contact Lens, 31(5), pp. 201-208.
- Liu, Y.M. and Xie, P. (2016) ‘The Safety of Orthokeratology–A Systematic Review’, Eye & Contact Lens, 42(1), pp. 35-42.
- Jung, S., Eom, Y., Song, J.S., Hyon, J.Y. and Jeon, H.S. (2024) ‘Clinical Features and Visual Outcome of Infectious Keratitis Associated with Orthokeratology Lens in Korean Pediatric Patients’, Korean Journal of Ophthalmology, 38(5), pp. 399-412.
- Van Meter, W.S., Musch, D.C., Jacobs, D.S., Kaufman, S.C., Reinhart, W.J., Udell, I.J. and American Academy of Ophthalmology (2008) ‘Safety of overnight orthokeratology for myopia: a report by the American Academy of Ophthalmology’, Ophthalmology, 115(12), pp. 2301-2313.e1.
- Butrus, S.I. and Klotz, S.A. (1990) ‘Contact lens surface deposits increase the adhesion of Pseudomonas aeruginosa’, Current Eye Research, 9(8), pp. 717-724.
- Yi, J., Sun, Y., Zeng, C., Kostoulias, X. and Qu, Y. (2023) ‘The Role of Biofilms in Contact Lens Associated Fungal Keratitis’, Antibiotics (Basel), 12(10), p. 1533.
![たける眼科 | 福岡市早良区 高取商店街[西新駅/藤崎駅]](https://takeru-eye.com/wp-content/uploads/2022/10/takeru_logo_for-WP-header.png)