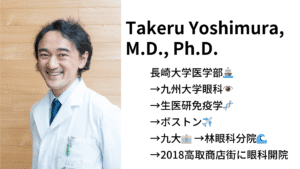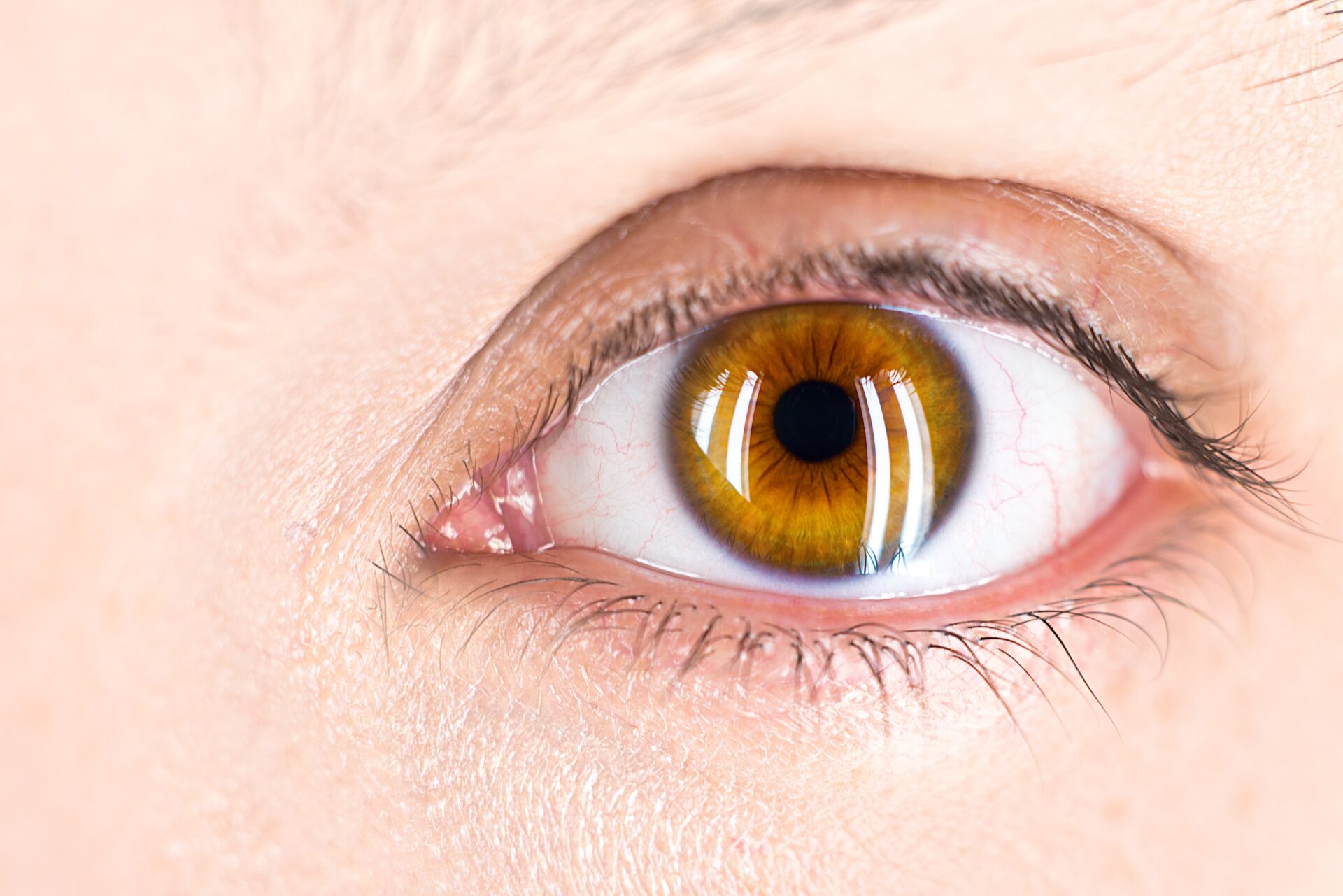「目が赤い」という症状で眼科を受診される患者さんは非常に多くいらっしゃいます。その原因は、ウイルスや細菌、アレルギーなどさまざまです。
ぶどう膜炎で目が赤くなることもあります。
たくさんの病気を想像しながら、判断されます。
ほとんどの結膜炎は、医師が症状や流行状況などをもとに判断し、特別な検査を必要としません。
しかし、症状が非常に重い場合や、なかなか治らない場合、あるいは角膜(黒目)にまで影響が及んでいるような特定の状況では、「グラム染色」などの検査が適切な治療方針を決めるための重要な手がかりとなります。
今回の記事は、感染性結膜炎に限定した一般的な話です。
結膜炎を診断する難しさ:初期症状と悪化の可能性
「今は症状が軽くても、後から結膜炎の症状が悪化することはよくあります。」
結膜炎は、最初は非常に軽い症状で始まることが少なくありません。
例えば、目が少し潤んだり、わずかにかゆみを感じる程度で、ご自身では気づかないこともあります。
しかし、これらの初期症状は数時間から数日かけて悪化することがあり、はっきりとした目の充血、目やに、痛み、場合によっては視力低下にまで至ることもあります。
特に、重症の細菌感染やアデノウイルスによる感染では、症状が強く出やすい傾向があります。
特に注意が必要な病気として、淋菌性結膜炎があります。
この病気は発症することはまれですが、非常に急速に悪化するため、眼科の緊急疾患とされています。
発症してから12~24時間以内に、大量の膿のような目やにや激しい充血、まぶたの大きな腫れなど、「超急性」と呼ばれる症状が現れるのが特徴です。
治療が遅れると、角膜(黒目)が溶けたり、穴が開いたりする危険性が高く、最悪の場合は失明することもあります。
そのため、このような症状が見られた場合は、すぐに専門医による診断(グラム染色で原因菌を確認)と、セフトリアキソンなどの全身的な抗菌薬の投与による治療が必要です。
「どんな経験を積んだ医師でも、最初に正確な原因を判断するのは難しいことも多いです。」
そのため、経験豊富な眼科医であっても、初診時に正確な原因を診断するのは難しいとされています。
なぜ、すべての結膜炎で検査をしないのか?
急性結膜炎の多くはウイルスが原因で、自然に治ることがほとんどです。
細菌が原因の場合でも、ほとんどは軽症であり、抗菌薬を使わなくても自然に回復することがわかっていますが、抗菌薬の使用で回復を早めることもできます。
そのため、米国眼科学会などの専門機関は、一般的な結膜炎の患者さん全員に対して、定期的に検査を行うことは推奨していません。検査は、以下のような特定の場合に検討されます。
- 重症の場合:大量の膿(うみ)のような目やにが出ている。
- 非典型的な場合:一般的な結膜炎とは様子が異なる。
- 治療に反応しない場合:処方された薬を使っても改善が見られない。
- 新生児の場合。
- 角膜炎が疑われる場合:黒目の部分にまで炎症が及び、視力に重大な影響を及ぼす可能性がある。
診断ツールを使い分ける
眼科感染症の診断には、いくつかの検査方法があり、それぞれに長所と短所があります。医師は状況に応じて最適なツールを選択します。
グラム染色が真価を発揮する時
グラム染色は、上記のような「特別な状況」において、迅速に結果が得られるため、治療の初期方針を決める際に非常に役立ちます。
視力を脅かす重症の細菌性角膜炎
角膜(黒目)が細菌に感染する「細菌性角膜炎」は、結膜炎とは異なり、緊急性の高い病気と判断されます。
この場合、グラム染色によって数分で細菌の有無や種類を推定することができます。
実際に、日本眼感染症学会の「感染性角膜炎診療ガイドライン」でも、細菌性角膜炎の診断には塗抹検鏡(グラム染色など)と培養検査を強く推奨しています。
見つけにくい病原体「微胞子虫」
まれなケースですが、「微胞子虫(マイクロスポリジウム)」という小さな寄生虫が角膜炎を引き起こすことがあります。
この診断でも、顕微鏡で直接病原体を確認する塗抹検査が非常に重要です。
もう一つの迅速検査:アデノウイルス迅速診断キット
「はやり目」(流行性角結膜炎)が強く疑われる場合、アデノウイルスを迅速に検出するための診断キットが用いられることがあります。
これらの検査は、クリニックで数分以内に結果がわかるため、アデノウイルスが原因かどうかを早期に確認するのに役立ちます。
診断が確定することで、ウイルス性の結膜炎と細菌性やアレルギー性のものとを区別し、不要な抗菌薬の使用を避けることができます。また、仕事や学校を休む期間の目安にもなります。
キットの感度(病気を見つける能力)にはばらつきがありますが、特異度(病気でないものを見分ける能力)は96~98%と非常に高く、陽性の場合の信頼性も高いです。
ただし、検査で陰性となっても、特に症状の初期や後期には、感染を完全に否定することはできません。

各検査の比較
| 診断方法 | 感度(病気を見つける能力) | 特異度(病気でないものを見分ける能力) | 所要時間 | 特徴 |
| グラム染色 | 36–75% | 83–98% | 数分 | 迅速で、細菌や一部の寄生虫の存在を強く示唆できる。ただし、感度は中程度。 |
| アデノウイルス迅速診断キット | 約90% (可変性あり) | 96-98% | 数分 | はやり目の迅速診断に有用。陰性でも感染を完全には否定できない。 |
| 培養検査 | 38–66% | 95–100% | 2–10日 | 原因菌を正確に特定でき、どの抗菌薬が有効かもわかる「ゴールドスタンダード」です。ただし、結果が判明するまでに時間がかかります。 |
| PCR検査 | 25–88% | 93–100% | 数時間–1日 | ウイルスや培養が難しい菌の検出に優れている。 |
結論:適切な場面で、適切な検査を
グラム染色は、すべての「赤い目」の患者さんに必須の検査ではありません。
日常的な多くの結膜炎は、医師の診察によって診断・治療されます。
しかし、グラム染色やアデノウイルス迅速診断キットなどの検査は、細菌性角膜炎が強く疑われる場合や、重症の結膜炎が考えられる場合に、迅速かつ的確な初期治療への道筋を示してくれる、非常に価値のある検査です。
最終的な診断は、医師の臨床的な判断を中心に、必要に応じてこれらの検査を組み合わせて行われます。
参考文献
- American Academy of Ophthalmology (2023), Preferred Practice Pattern: Conjunctivitis.
https://www.aao.org/preferred-practice-pattern/conjunctivitis-ppp - Azari, A.A. and Barney, N.P. (2013), ‘Conjunctivitis: a systematic review of diagnosis and treatment’, JAMA, 310(16), pp. 1721-1729.
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1760021 - Centers for Disease Control and Prevention (2021), Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/gonorrhea-adults.htm
- Cholkar, K. and Das, S. (2021), ‘Emerging trends of ocular microsporidiosis’, Frontiers in Medicine, 8, p. 646845.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2021.646845/full - EyeWiki (2024), Epidemic Keratoconjunctivitis.
https://eyewiki.org/Epidemic_Keratoconjunctivitis - Gurnani, B. and Gireesh, P. (2024), ‘Gonococcal Conjunctivitis’, StatPearls [Internet]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459289/
- Gurnani, B. and Mahajan, K. (2024), ‘Bacterial Keratitis’, StatPearls. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK546687/
- 日本眼感染症学会感染性角膜炎診療ガイドライン第3版作成委員会 (2023), ‘感染性角膜炎診療ガイドライン(第3版)’, 日本眼科学会雑誌, 127(10), pp. 859-903.
https://www.nichigan.or.jp/member/journal/guideline/detail.html?itemid=672&dispmid=909 - Joseph, J., Murthy, S.I., Garg, P. and Sharma, S. (2013), ‘Microsporidial keratitis: clinical features, unique diagnostic criteria, and treatment outcomes’, Ophthalmology, 120(8), pp. 1548-1553.
https://www.aaojournal.org/article/S0161-6420(13)00078-6/fulltext - Kudo, T., et al. (2011), ‘Performance evaluation of detecting adenovirus by rapid diagnostic kits for ophthalmologic use in Japan’, Journal of clinical virology, 53(3), pp. 217-220.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22173876/ - Moshirfar, M., et al. (2019), ‘Biological Staining and Culturing in Infectious Keratitis’, Clinical Ophthalmology, 13, pp. 1999-2015.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6778464/ - Sharma, S. (2009), ‘Diagnostic techniques in microbial keratitis’, Current Opinion in Ophthalmology, 20(4), pp. 283-289.
https://journals.lww.com/co-ophthalmology/abstract/2009/07000/diagnostic_techniques_in_microbial_keratitis.5.aspx - Sheikh, A., Hurwitz, B. and van Schayck, C.P. (2012), ‘Antibiotics versus placebo for acute bacterial conjunctivitis’, Cochrane Database of Systematic Reviews, (9).
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD001211.pub3/full
![たける眼科 | 福岡市早良区 高取商店街[西新駅/藤崎駅]](https://takeru-eye.com/wp-content/uploads/2022/10/takeru_logo_for-WP-header.png)