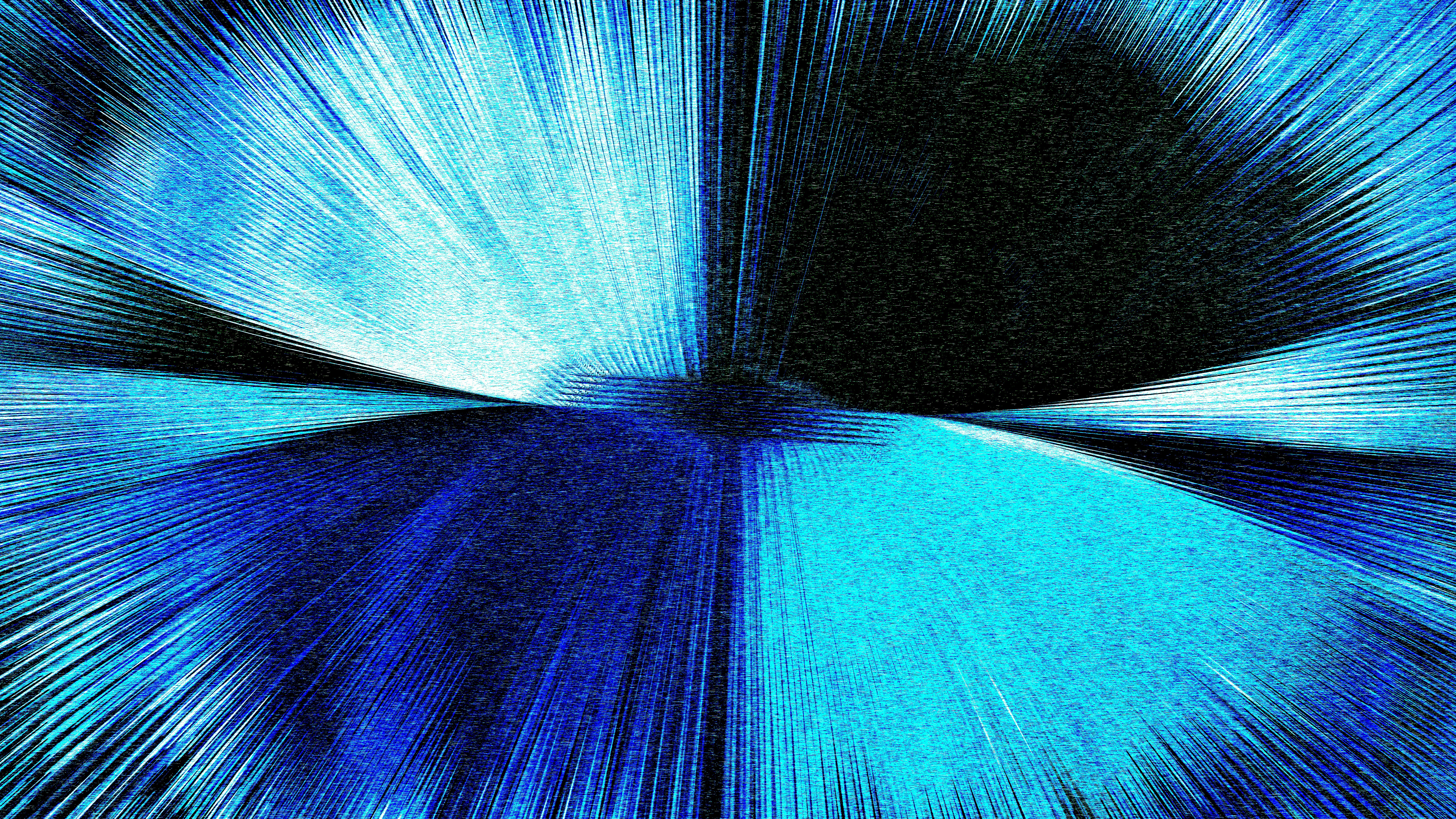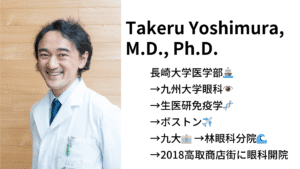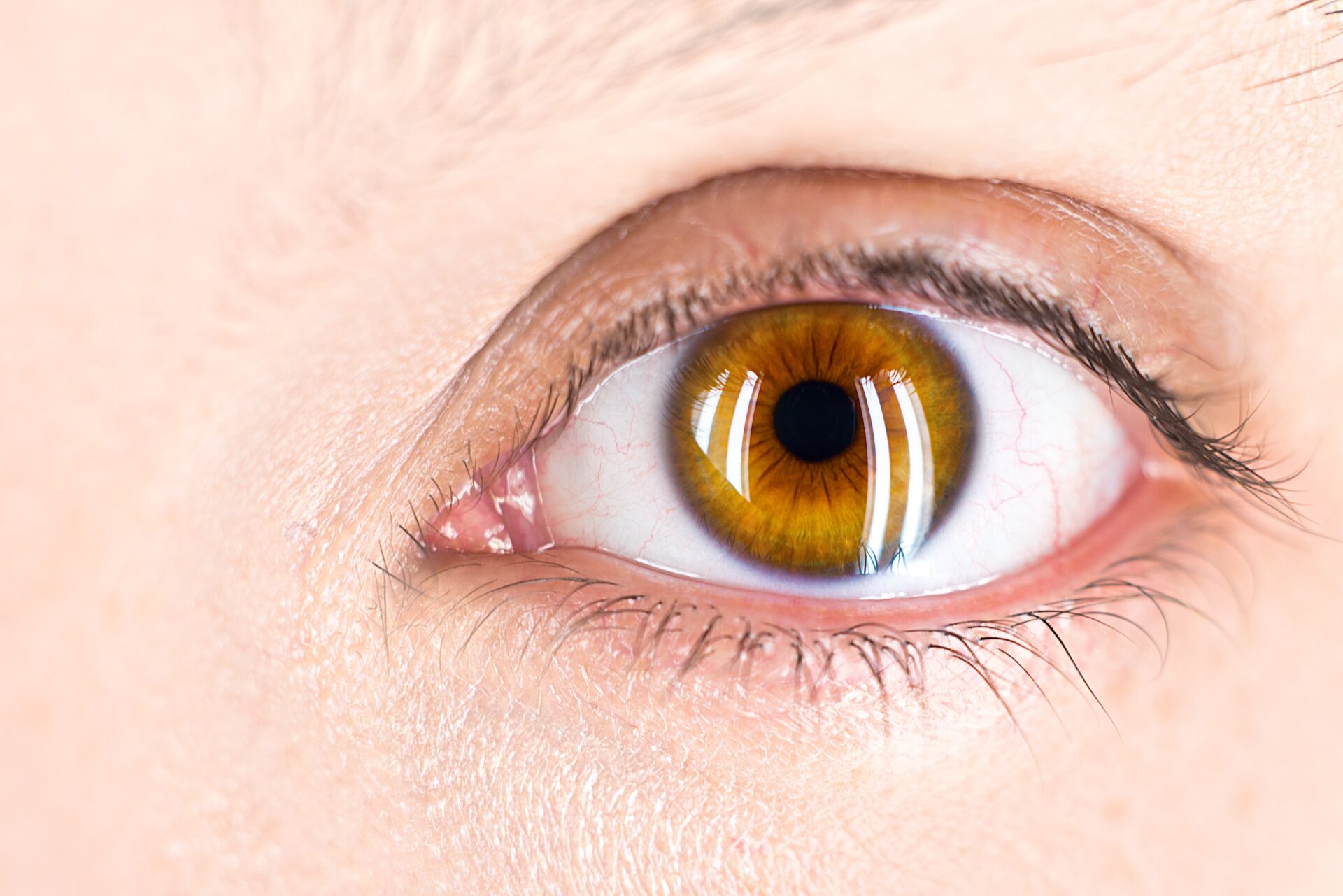「仕事が忙しくて通院できないので、いつもの目薬だけ処方してもらえませんか?」
このようなご相談は、眼科クリニックの日常的な場面でよくいただきます。特にコロナ禍を経てオンライン診療が広まったことで、「薬だけ欲しい」「オンラインで簡単に済ませたい」と期待される患者さんが増えています。
そのお気持ちはとてもよく理解できます。しかし、眼科では原則として「診察なしで薬を処方すること」はできません。これは医療機関側の都合ではなく、法律および患者さんの安全を守るために定められた重要なルールです。
医師法という法律で「医師は診察をしないで処方箋を交付してはならない」と定められており、違反すれば罰則があります1。また、眼科診療では目の中を詳しく調べるための特殊な検査機器が不可欠であるため、オンライン診療にも厳しい制限が設けられています。
この記事では、なぜ眼科で「薬だけ」が難しいのか、オンライン診療では何ができて何ができないのか、そして本当に来院が困難な場合の安全な方法について、法律と医学の両面から詳しく解説します。
医師法第20条─「診察なし」の処方は違法行為
まず知っていただきたいのは、「診察をせずに薬を出す」という行為は、医師法第20条という法律で明確に禁止されている違法行為だということです1。
医師法第20条には「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付してはならない」と書かれています。
これを破った場合、医師には50万円以下の罰金が科され、さらに医師免許の停止や保険医の取り消しといった行政処分を受ける可能性があります2。
「いつも使っている薬なのだから、同じものを出すだけなら問題ないのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、法律では新しい薬であっても継続して使っている薬であっても、すべての処方で「医師の診察」が義務付けられています。
この規定は、患者さんの命と健康を守るための最低限の安全装置です。
コロナ特例の終了─「あの時は出してもらえたのに」の理由
2020年から2023年7月まで、新型コロナウイルス感染症への対応として、オンライン診療のルールが一時的に大幅に緩和されていました3。
この期間は「0410通知」と呼ばれる特例措置により、初診からのオンライン診療や、電話のみでの診療も例外的に認められていました。
「以前は電話で薬を出してもらえたのに、今回は断られてしまった」というご経験をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
これは、コロナ特例が終了し、現在は通常通り厳格なルールに戻ったためです3。
現在のルールでは、オンライン診療が「診察」と認められるためには、単なる電話や文字のやり取りではなく、リアルタイムのビデオ通話を使って、医師が「十分な医学的情報が得られる」と判断した場合に限られています4。
眼科診療の特殊性─「外から見るだけ」では分からない
では、ビデオ通話で医師が患者さんの目を画面ごしに確認すれば、それだけで「診察」が成立するのでしょうか?
残念ながら、眼科ではそれだけでは不十分です。
眼科の診断や治療には、クリニックに備わる特殊な検査機器が必ず必要となるからです。
ビデオ通話で見えるのは「表面」だけ
オンライン診療のビデオ通話で確認できるのは、まぶたの腫れや目の充血など「見た目の変化」に限られます。
しかし、眼科診療で本当に重要なのは、目の内部の状態です。
眼科診療に必須の検査として、以下のようなものがあります。
眼圧測定: 目の硬さ(圧力)を測定します。緑内障の診断と管理に欠かせません。
細隙灯顕微鏡検査: 特殊な顕微鏡で、角膜の傷、目の中の炎症、水晶体の濁りなどを詳しく観察します。
眼底検査: 網膜や視神経の状態を確認します。糖尿病網膜症、緑内障、網膜剥離などの診断に必要です。
これらの検査は、すべてクリニックに来院しなければ実施できません。
アメリカ眼科学会(American Academy of Ophthalmology, AAO)も、オンライン診療では細隙灯顕微鏡検査などが行えないといった限界があり、医師がその点を患者さんに明確に伝える義務があると指摘しています5。
特に危険な2つのケース─自覚症状がない病気の恐ろしさ
眼科診療で最も難しいのは、患者さんの自覚症状と病気の重症度が一致しないという点です。
「見え方に問題がない」「痛くない」からといって、目が健康とは限りません。
オンライン診療で特に危険なのが、次の2つのケースです。
ケース1: ステロイド点眼薬─3人に1人が眼圧上昇のリスク
リンデロン、フルメトロンといったステロイド点眼薬は、アレルギーや炎症を抑える非常に効果的な薬です。
しかし同時に、重大な副作用として「眼圧上昇」を引き起こすリスクがあります。
研究によれば、一般の人の約30%がステロイドに反応して眼圧が上昇する体質(ステロイドレスポンダー)であり、そのうち5〜6%は15mmHg以上の大幅な上昇を示します6。
問題なのは、眼圧が上がっても患者さんには何の自覚症状もないという点です。
気づかないまま眼圧が高い状態が続くと、視神経が徐々に損傷を受け、最終的には緑内障を発症してしまうことがあります。
また、一度失われた視野は回復しません。
日本眼科医会と日本緑内障学会は共同で、「ステロイド点眼は眼科での治療が必須である」「定期的な眼圧測定が重要」と強く警告しています7。
オンライン診療では眼圧を測定できません。
そのため、眼圧測定を行わずにステロイド点眼薬をオンラインで処方することは、患者さんを失明のリスクにさらす危険な行為です。
ケース2: 緑内障治療薬─「薬を使っている」≠「治療できている」
緑内障は、自覚症状のないまま視野が少しずつ欠けていく病気です8。
治療の目的は、眼圧を下げることで視野の欠損が進行しないように管理することです。
緑内障治療では、定期的な眼圧測定、視野検査、光干渉断層計(Optical Coherence Tomography, OCT)による視神経の評価が必要です9。
これらの検査によって初めて、「今の治療が効いているか」「病気が進行していないか」を判断できます。
オンライン診療で患者さんが「いつもどおり目薬を使っています」「特に変わったことはありません」と報告しても、それだけで治療が順調に行われているとは限りません。
眼圧が目標値に達していなければ、患者さんが自覚しないまま病気は静かに進行します。
法律的な観点から見ても、患者さんの利便性だけを重視した安易な処方の継続は、医師にとって非常に大きな法的リスクにつながります。
初診で誤診した場合よりも、定期的な検査を怠って既知の病気が悪化したほうが、医療過誤として責任を問われやすくなります。

オンライン診療が「成立する」限られたケース
では、眼科のオンライン診療は全く意味がないのでしょうか?
そんなことはありません。
以下のように、「軽症」でありかつ「外見からの観察」で判断できる場合に限り、オンライン診療が成り立つ可能性があります。
既知のアレルギー性結膜炎(軽症): 以前から診断がついており、花粉症の時期にいつものアレルギー用目薬(ステロイドを含まないもの)が必要な場合10。
麦粒腫(ものもらい)の初期: まぶたが少し赤く腫れ始めた段階で、ビデオ通話で明らかに「ものもらい」と判断できる場合11。
結膜下出血: 白目が真っ赤に染まったが、痛みも視力低下もない場合。
ただし、これらのケースでも大切な条件があります。
それは「症状が2〜3日以内に改善しない場合や悪化した場合は、すぐに対面診療を受ける」という決まりを守ることです。


「充血」に潜む重篤な病気─見逃しの危険性
「目が赤い」「充血している」という症状は、一見すると軽い問題に思えるかもしれません。
しかし充血は、失明に至る重篤な病気の初期症状でもあります。
特にコンタクトレンズを使用している人の充血は要注意です。
角膜潰瘍、特にアカントアメーバ角膜炎のような重篤な感染症のリスクが非常に高いからです12。
ぶどう膜炎も、最初は充血から始まることが多いです。
ヘルペスウイルスによる目の炎症も多くみられます。
日本眼科学会も、「目のかゆみや充血は様々な疾患で見られ、原因がアレルギー性結膜炎であるかは専門医でも鑑別が難しい場合がある」と指摘しています10。
ビデオ通話では、細隙灯顕微鏡による角膜の傷の有無、目の中の炎症細胞の確認、眼圧の測定ができません。
こうした検査を行わず、単なる「充血」と判断して抗菌薬や抗アレルギー薬を処方してしまうと、重大な病気を見逃すリスクが生じます。


本当に来院できない場合の安全な選択肢
「法律や安全性については理解しました。それでも、どうしても来院できない事情がある場合は、どうすれば良いでしょうか?」
そのような患者さんのために、「薬だけ」という危険な方法の代わりに、安全で合法的な選択肢があります。
選択肢1: 往診・訪問診療
寝たきりの状態、または通院の負担が非常に大きい患者さんには、医師がご自宅や施設に伺う往診(訪問診療)という方法があります13。
現代では、持ち運び可能な眼圧計や小型の細隙灯顕微鏡が存在します。
医師がこれらの機器を持参することで、クリニックと同等に近い診察が可能になります。
特に認知症などで診察への協力が難しい患者さんの場合、オンライン診療よりも往診の方がはるかに有効です。
選択肢2: 対診(医師間の連携)
他の病院に入院中、または介護施設に入所中の患者さんの場合、患者さんと眼科医が直接ビデオ通話をする(医師-患者モデル)のではなく、現地の主治医と眼科医が連携する「対診」という方法が適切です1。
現地の主治医が患者さんを診察し、その情報(例:「右目の充血や膿性の目やにがある」など)を眼科医に提供します。
眼科医はその情報に基づいて専門的なアドバイスを行い、処方箋は現地で患者さんを実際に診察した主治医が発行します。
この方法であれば、医師法第20条に定められた「自ら診察しないで処方してはならない」という規定には該当しません。
選択肢3: 緊急時の「つなぎ処方」
これは極めて例外的な対応ですが、緑内障などで服薬が途切れることによる重大なリスクが差し迫っている場合に限り、次の対面診療までの「つなぎ」として最小限の日数分のみを処方する方法があります。
ただし、これは厳格な条件を満たす必要があります。
患者さんご本人との電話やビデオ通話で服薬状況や副作用の有無を確認すること、対面診療の予約を確実に取ること、処方は次回の予約日までの最短日数(例:7日分)に限定すること、などです。
これはあくまで患者さんの薬の中断によって生じる視神経障害を防ぐための、緊急時のみ認められる例外的な対応です。
利便性だけを目的とした処方ではありません。
「家族だけ」が来院して薬をもらう方法は?
「本人が行けないので、家族だけが病院に行って薬をもらいたい」というご希望を持つ方もいらっしゃいます。
しかし、これも医師法第20条の「自ら診察しないで」に該当するため、原則として認められていません14。
患者さんご本人を診察することが、法律上の絶対条件となっています。
どうしても来院が難しい場合は、先述の往診や対診など、安全な方法を検討することが必要です。
監査と行政処分─医療機関側のリスク
厚生労働省は、不適切なオンライン診療(文字のみのやり取り、指針違反の初診など)に対して、都道府県を通じて実態調査と指導を行っており、悪質な場合は業務停止勧告などの行政処分を行います15。
2023年度には、診療報酬の不正請求などに対する監査が46件実施され、そのうち21件が「保険指定取り消し」などの処分を受けています2。
医師法第20条違反(無診察投薬)は、保険診療のルール違反(不正請求)と表裏一体です。
必要な検査を実施せずにオンライン診療料を請求し、処方箋を交付し続ける行為は、監査において重大な指摘事項となり得ます。
患者さんから見ると、「薬だけを出してくれる便利な病院」は一見ありがたく感じられるかもしれません。
しかし実際には、必要な検査を省略することで重大な病気の発見が遅れたり、副作用に気づけなかったりするリスクがあります。
また、医師法で定められた「診察」の要件を満たさない処方は、法的にも問題があるとされています。
表面的な利便性の裏には、患者さんご自身の目の健康と法的な安全性、両方を守るための大切な確認が欠けている可能性があるのです。
医師が「診察」として記録すべき内容
オンライン診療を行った場合、医師には通常の対面診療以上に詳しい記録が求められます。
これは単なる診療記録ではありません。
「なぜオンライン診療が可能だと医師が判断したのか」を証明するために必要な法的な文書でもあるのです。
記録には以下の要素が必須です。
患者さんへの説明と同意: オンライン診療の限界(眼圧測定や細隙灯検査ができないこと)を説明し、患者さんが理解した上で希望したこと。
本人確認: 保険証や運転免許証による確実な本人確認。
診察方法: リアルタイムのビデオ通話システムを使用したこと。
視診所見: ビデオ通話で確認できた内容と、確認できなかった内容の両方を明記。
医師の判断根拠: なぜ安全と判断したか、どのような指導を行ったか。
対面診療への移行基準: 症状が改善しない場合や悪化した場合は直ちに対面診療を受けるよう指示したこと。
このような詳細な記録は、万が一トラブルや監査が発生した場合に、医師が適切な医療を行ったことを証明するための唯一の手段となります。
今後の展望─技術進歩と制度のバランス
将来的には、自宅で眼圧を測定できる機器やスマートフォンに接続できる眼底カメラなどの技術が普及する可能性があります。
そうなれば、オンライン診療でも対面診療に近い精度で情報を得られるようになるかもしれません。
しかし現時点では、そのような技術はまだ一般化していません。
今後技術が発展しても、医師法第20条で定められた「診察」の基準は変わりません。
つまり、医師が十分な医学的情報を得られると判断できる環境が整わない場合は、安易に薬を処方することはできません。
オンライン診療はあくまでも対面診療を「補完」するものであり、「代わり」にはなりません。
この原則が、患者さんの安全を守る上でとても重要なのです。
まとめ─安全と利便性のバランス
この記事では、眼科で「薬だけください」が難しい理由について、法律と医学の両面から解説してきました。
重要なポイントをまとめます。
- 医師法第20条により、診察なしでの処方は違法行為です。これは新しい薬でも継続の薬でも同じです。
- 眼科診療には、眼圧測定や細隙灯顕微鏡検査といったクリニックでしか実施できない検査が不可欠です。
- ステロイド点眼薬や緑内障治療薬のオンライン処方は、失明につながる危険性があります。
- 軽症のアレルギーや麦粒腫など、限られたケースではオンライン診療が可能な場合もあります。
- 本当に来院が困難な場合は、往診・対診・緊急時のつなぎ処方といった安全な選択肢があります。
「診察なしで薬を出してくれる便利なクリニック」は、一見親切そうに思えるかもしれません。
しかし、そうしたクリニックは、法律を守らず患者さんの安全を軽視している場合があります。
逆に「診察が必要です」と説明するクリニックは、不便に感じるかもしれませんが、実際には患者さんの目の健康を守るために真摯に責任を果たそうとしているのです。
私たち眼科医が「診察が必要」と申し上げるのは、決して患者さんにご不便をかけたいからではありません。
大切な「見る権利」と「目の健康」を守るために、法律と医学の両面から必要な手順なのです。
参考文献
- 厚生労働省. 医師法. e-Gov法令検索.
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000201 - 厚生労働省. 令和5年度 保険医療機関等の指導・監査実施状況.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa.html - 厚生労働省. オンライン診療の適切な実施に関する指針.
https://www.mhlw.go.jp/content/000889114.pdf - 厚生労働省. 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A.
https://www.mhlw.go.jp/content/000889116.pdf - American Academy of Ophthalmology. Telehealth for Ophthalmology.
https://www.aao.org/clinical-statement/telehealth-ophthalmology - Armaly MF. Effect of corticosteroids on intraocular pressure and fluid dynamics. Arch Ophthalmol. 1963;70:482-491.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14078870/ - 日本眼科医会・日本緑内障学会. ステロイド緑内障に関する啓発資料.
https://www.gankaikai.or.jp/info/20250401_steroid.pdf - Weinreb RN, Aung T, Medeiros FA. The pathophysiology and treatment of glaucoma: a review. JAMA. 2014;311(18):1901-1911.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24825645/ - Tham YC, Li X, Wong TY, et al. Global prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through 2040. Ophthalmology. 2014;121(11):2081-2090.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24974815/ - 日本眼科学会. 一般用医薬品等に関する見解.
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001509870.pdf - Lindsley K, Nichols JJ, Dickersin K. Non-surgical interventions for acute internal hordeolum. Cochrane Database Syst Rev. 2017;1(1):CD007742.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28068454/ - Dart JK, Saw VP, Kilvington S. Acanthamoeba keratitis: diagnosis and treatment update 2009. Am J Ophthalmol. 2009;148(4):487-499.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19660733/ - 厚生労働省. 在宅医療の推進について.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061944.html - 厚生労働省医政局医事課長通知. 医師法第20条に関する解釈について.
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb8648&dataType=1&pageNo=1 - 厚生労働省. 地域医療構想の見直し等② オンライン診療に関する総体的な規定の創設
https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001442574.pdf
![たける眼科 | 福岡市早良区 高取商店街[西新駅/藤崎駅]](https://takeru-eye.com/wp-content/uploads/2022/10/takeru_logo_for-WP-header.png)